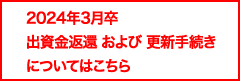2019年7月3日(水)近藤雄生さんトークイベントレポート
雨模様の夕方、近藤雄生さんの『吃音』刊行記念トークイベントが開催されました。

メディアでも評判になっているこの本には、みなさん関心が高く60名もの方々が駆けつけてくださいました。

こんにちは。ライターの近藤雄生です。自分はもともと、物理学者や宇宙飛行士に憧れた理系の人間で、本や文章とは縁遠いまま大学まで過ごしました。大学に入ってはじめて本を面白いと感じ、興味を持つようになったのですが、その後、進路を考える段階になって、いくつかの理由から、就職はしないで、旅をしながら文書を書くライターになろうと思い立ちました。東南アジアだと100万円あれば2~3年暮らして行けるし、きっと書くべきネタもいろいろある。そして、単純に旅をして暮らすのは楽しそうだと感じてのことです。自分にとっては、日本に暮らしながらライターを目指すよりずっと可能性があるように感じられました。
旅立ちは2003年、26歳の時、大学院の修士課程を修了した翌年のことでした。付き合っていた一つ年上の彼女も同じように長い旅をしたい人だったので、結婚して二人でいくことにしました。そして結婚3か月後に二人で日本を発ちました。結局その旅は、オーストラリア、東南アジア、中国、ユーラシア大陸で、住んだり移動したりを繰り返して、5年以上続きました。日本に帰ってきたのは2008年のことでした。
旅の最初、オーストラリアでは、西海岸のバンバリーで、イルカにかかわるボランティア活動をしながら暮らしました。宿屋で2時間働いて宿代をタダにしてもらって住み、あとは、人に会って取材らしきこともしていました。とはいえ、このころはまだ書いて仕事になるような段階ではなかったですが。
そして半年ほどバンバリーで過ごしたあとは、7万円でニッサンの古いバンを買ってオーストラリア大陸を縦断しました。1カ月半がたって大陸北端のダーウィンに着いたときには、車のエンジンもだいぶおかしくなっていましたが、修理屋さんで直してもらい、12万円で売ってバンの旅を終えました。
次は東ティモールへ。当時この国は、独立2周年を迎えようというころで、世界で一番新しい国として知られていました。まさに国づくりの最中で法律も未整備。免許制度も信号もない状態でした。そして隣国のインドネシアでは、ラマレラという伝統捕鯨で知られる小さな村にいってイルカ漁の現場を目の当たりにしたりしました。その後、マレーシア、タイ、ミャンマーといった国々を経ながら東南アジアを縦断して、ラオスから中国の雲南省にたどり着きました。

雲南省の省都である昆明(クンミン)に住むことになったのですが、ここは気候もよくて物価も安い、居心地のよいところで結局1年間滞在しました。留学生のビザを取って、大学に通い、中国語も学びました。
しかし、当時29歳で、収入は1年で30万円ぐらいしかなく、物書きとして生活できている状態ではなく、人生これで大丈夫なのだろうかと、色々悩んだりもしていました。その上、血便が出て、さらには回虫も出てきて、病院で大腸内視鏡検査をしたら、ポリープも見つかって、手術をすることになりました。現地での大腸内視鏡検査は、痛いか、痛くないかを選べるワイルドな方式で、手術後には病院で、ギトギトの青椒肉絲が出て来たりという驚くべき感じでしたが、まあ、なんとかなって、自分としては、その力の抜けた感じが肌にあいました。
昆明のあとは、妻が中国で仕事をしたいということになり、上海へ移住しました。そして妻が企業に勤め、ぼくは配偶者ビザでの滞在という形で、上海で1年半暮らしました。ここで自分もようやく、文章を書いて食べていけるようになりました。日本人の駐在員の子どもの家庭教師も週2回ぐらいやっていましたが。
そして上海の後、ユーラシア大陸横断へ。中国、モンゴル、ロシア、中央アジア各国、イラン、アルメニア、グルジア、トルコ、ギリシャ、イタリア......という具合でヨーロッパまで行きました。途中チベットで高山病になったり、トルコでは、ヒッチハイクを繰り返したり。ヨーロッパでは、スイス、オランダなどの友人宅に泊めてもらいながら、半年近く滞在し、中国のように住むことも考えましたが、気力体力ともに疲れていて、日本に帰ることに決めました。その後、最後にアフリカによってから、2008年に日本に帰ってきたのでした。
旅を終えるころには、物書きとしてそれなりに収入が得られるようになっていました。200万円をもって日本を出たのですが、帰る時にはまだ100万円ほど残っていました。旅の5年半で稼いだお金は500万、使ったお金は600万円ほどでしかありませんでした。

帰国後、いきなり日本で物書きとして食べていけるとはとても思えず、とりあえず派遣に登録して就職活動を始めました。しかし、どの会社も、会ってもくれないという現実に直面して、それならば文章を食べていくしかないと、覚悟を決めました。
そして結果、本を出す機会にも恵まれたりするうちに、なんとかライターとして生活していけるようになったのでした。
ところで、自分が、就職をせずにライターとして旅をするというような、ある意味大胆な進路を選ぶことになったのには、大きな理由がありました。それが「吃音」、つまりどもってうまくじゃべれないということでした。ぼくは高校時代からその症状に悩まされていました。
例えばファストフード店に行ったとします。「てりやきバーガー」が食べたいと思ってもどうしても「て」が言えなくなったりして、その時、ぱっと言えそうな言葉を探した結果、「チーズバーガー」と言ってしまったりしました。
また、駅で電車を乗り換える際に、目的の駅名を口頭で言わないといけないというような場所では、駅名が言えなくなるような気がして、いつもいったん改札を出て新たに切符を買ったりしていました。また電話もずっと苦手だったため、大学院の時には、研究室の電話が鳴るのが怖くて、電話がなったらどうしよう、といったことばかり考えていました。そして、こんなだったら会社に入っても思い切り働くことはできないだろうと考えて、就職はせずにフリーで生きていくという方法を考えるようになったのでした。
吃音の人は100人の一人と言われています。日本では100万人の人に吃音があるという計算になります。有名人の中では、マリリン・モンローも吃音と言われていますし、ブルース・ウィルスは、唯一演技しているときだけどもらなかったということで、役者になったそうです。アナウンサーの小倉智昭さんも、テレビでは一切わかりませんが、吃音で悩んでこられたことで知られる人です。
さて、では、自分の吃音はいまどうなっているのかといえば、じつは、中国の昆明に住んでいた時、ある一週間ぐらいを境に突然に消えていったのでした。急に話しやすくなった瞬間があり、それから浮き沈みはありましたが明らかに軽減していって、さらに6,7年経ったころに、ほぼ吃音で悩むことはなくなりました。その変化がなぜ起こったのかは、いまだ自分にもわかりません。
どもるということは、他の人から見たら、一見たいしたことには見えないかもしれません。でもそれが原因で自殺する人もいるなど、時に人生に極めて深刻な影響を与えるほど、当事者は深く悩んでいる場合があります。当事者の、そのような知られざる苦悩を知ってもらいたいと思い、『吃音』を今年1月に出しました。伝えたいという気持ちがあるのに伝えられないというのは、想像以上に苦しいことなのです。

先日、作家の重松清さんとトークイベントをやらせていただく機会がありました。重松清さんも吃音の当事者で、そうしたテーマの小説も書かれています。また作家になられたのも、吃音があることと大きく関係しているとのことでした。その時、会場から、吃音があって作家であるいまの人生と、吃音がなく作家でもない人生のどちらかを選べるとしたら、という質問がありましたが、重松さんは、きっと作家でもなく、吃音でもない人生を選ぶだろうとのことでした。重松さんほどの大作家がそのようにおっしゃるのを聞いて、吃音の苦悩というのがいかに重いものかを改めて感じさせられました。しかし重松さんは、こうもおっしゃっていました。吃音があってよかったとは言えない。でも、吃音がある人生も悪くはないといまは思うと。
ぼく自身にとっても、吃音で悩んできた経験は、文章を書こうと思ったこととおそらく少なからず関係しています。また、吃音の経験が、自分の文章そのものにも色々と影響を与えていることも確かです。自分が吃音で深く悩み、でも、周囲にはそのことはほとんど知られていなかったという経験から、他の人がどんなことで悩んでいるかは容易にはわからないものだという気持ちをぼくはいつも持っています。それが、人の話を聞く上での根本にあり、自分の書く文章の核にあるような気がします。
そのように、自分にとって、これまでの人生の最も深いところのあったのが吃音というテーマです。それを自分なりの方法で世に問いたいと思って書いたのが、この『吃音』という本なのです。
また、自分にとっての吃音のようなコンプレックスは、誰にでも多かれ少なかれあるものだと思います。そしてその悩みは、たとえ周囲の人から見たらそんなに大した問題ではないように思えても、本人にとってはとても深刻である場合も多いはずです。
そのようなコンプレックスから、逃げることは悪いことではないとぼくは思います。コンプレックスから逃げて、自分が生きやすい道を探すことで、いい道が開けていくこともきっとあります。また、コンプレックスが十人十色であるように、生き方も本来はそれぞれ違っていいはずです。しかし今は、進路を考える上でも、一本のレールのような画一的なシステムがあまりにも出来あがりすぎているように感じます。それゆえに、もし何か、一般的な就職活動をするのとは違う道に進みたいと思っても、その流れから抜け出すのは、ぼくが大学生だった時代よりも大変になっているように思います。それでも、ただみながやるからとやるというのは避けて、自分が何をやりたいかに素直に生きてほしいと思います。いわゆる就職活動をして就職するというのは、たくさんある生き方の中の一つでしかありません。そのことを意識してほしい。それを実感するためにも、大学時代に一度システムから出てみるような経験をしてみてください。旅はそのためにすごくいい方法です。
そして、自分が進みたいと思う道を、是非思い切って突き進んでください。頑張れば必ずうまくいく、とは限りません。でも、やりたいと思うことを突き詰めて、考え、もがき、動いていけば、その過程できっと、周囲に網目のように、たくさんの新たな世界、生き方、出会いが見えてくるはずです。みなさんの大学時代、陰ながら応援しています。
ここで近藤さんのお話は終わりました。次に質問コーナーです。
質問:吃音というのは見えない障害といえるかと思います。自分の知り合いにも吃音の人がいます。接するときに心がけることがあれば教えてください。
回答:例えばその人がお店での注文において、「コーヒー」と言いたくても言えずにいるとします。その時その人にとって、代わりに「コーヒー」と言った方がいいのか、だまって待っていた方がいいのか。それは人によっても状況によっても、おそらく違ってきます。それゆえ、この場合はこうすればいい、というマニュアルのようなものはありません。当事者がどうしてほしいのかは人それぞれです。相手が何を望んでいるのか、真剣に考えて、自分がいいと思ったことをやるしかないとぼくは思います。その結果、対応を間違えてしまうこともあるでしょう。当事者もまた、その場合には寛容であってほしい。大切なのは、当事者も非当事者も、相手に対してできるだけ想像力を働かせて行動し、同時に、お互いの理解の難しさを理解し合い、相手に寛容になることだと思います。それは吃音という問題を超えて、人と人がコミュニケーションをとるあらゆる場合に共通することだと思います。
質問:近藤さんは、海外に長く行かれていたとのことですが、外国語でも、どもったりしましたか。
回答:どもる感覚は同じでした。英語や中国語は、日本語に比べて自分の知っている語彙が少ないために、言い換えがうまくできず、どもって言えなくなったら黙るしかない、という難しさはありました。その一方、英語や中国語でどもってうまく言えなかったとしても、「この人は英語が分からないのだろう」などと思ってもらえるという気楽さがありました。それが自分にとって外国が居心地がいい理由の一つでした。
質問:自分も吃音があります。エンジニアの仕事をすることになりました。もし吃音を理解しようとしてくれない上司などがいたら、働く中で難しさは出てくるように思います。そのような中で、吃音とどう向き合えばいいでしょうか。
回答:どうしたら理解してもらえるか。働きやすくなるか。明確な解決方法がなく、ケースバイケースで、難しいなといつも思います。ただ、自分としてはどちらかといえば、カミングアウトすること、つまり周囲の人に自分の問題を伝えて、理解してもらうように努めることがよいのかなと感じます。本人の気持ちもあるので一概にはいえませんが。ただ、もし苦しいと思った場合には、やめるという選択肢も持っておくのが良いと思います。辛かった逃げる。それは決して悪いことではないので。逃げることで、新たに人生が開ける場合も少なくないと思います。
質問:吃音の方への支援というのは現在どうなっているのでしょうか。
回答:ここ4,5年で状況はだいぶ変わってきたように思います。吃音がある人に対して、会社や学校が、必要に応じて何らかの配慮をするようにと、法律の整備も進んでいます。社会の理解も少しずつ広がっているはずです。希望を持っていいようにも感じています。
質問:将来、本(ミステリ)を書いてみたいと思っています。ものを書く上で大切なことを教えてもらえますか。
回答:文章を書く上で大切なことは、何よりも文章の誠実さだと思います。取材相手や読者への誠実さ。フィクションでもノンフィクションでもそれはきっと同じです。言葉で伝えるということにどう誠実に向き合えるか。いまうまく言葉で表現できませんが、その誠実さのようなものは文章の細部に表れます。文章というのは、ちょっとした言葉の使い方や語尾などに、その人が現れる。それが文章の怖さであり、面白さであると思います。
質問:近藤さんの今後の予定、次の作品について聞かせていただけますか。
回答:『吃音』は、自分にとって一番切実なテーマを扱った本でした。これからもそのように切実なテーマを書いていきたい。でもそれが何なのか、いまはまだわからずにいます。吃音というテーマについても、当事者として様々な場で、発信したりを続けていくつもりです。
質問:文章を書く方として、近藤さんにとって「言葉」とはどういうものだと思いますか。
回答:一言ではなかなか言えませんが、言葉には、人の救いになる大きな力がある一方で、暴力的な側面も大きい。その負の面も十分に意識しながら、自分なりに、誠実に、伝えるべきことを伝えていきたいと思っています。


熱烈な質問コーナーのあと、『吃音』をきっかけとしてふらっとで展開中の「生きづらさを考える」フェアが紹介され、その場で『吃音』が8冊購入されました。






最後に10人以上の参加者の方が近藤さんの著作にサインを求められました。
熱心に話しかけている参加者もいて、近藤さんは丁寧に答えてらっしゃいました。
充実した時間をありがとうございました。