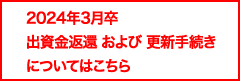理事長の講評
2020年度立命館コメント大賞にご応募くださった皆さん、まことにありがとうございました。
今年度はコロナ対策で入構が制限されたり、WEB授業のため大学に来なかったり、という環境の中で真摯に読書し、読書の喜びを多くの人と分かち合おうとする、みなさんの熱い気持ちが応募作にも表れていたように思います。
応募状況はKIC46通、BKC7通、OIC2通、APU0通の合計55通、19名の方々からの応募がありました。コロナ対策のため学内人口が減少したため、店舗での応募数は減ってしまいましたが、WEBでの申し込みは10通中7名あり、今後の取り組みとして重視したいと考えています。
教員と生協職員からなる6名の選考委員により、今回はペンネーム「ナス星人」さんの三島由紀夫著『命売ります』がグランプリに選ばれました。「ナス星人」さんは他にも安倍公房著『砂の女』など、昭和の重要な作家を紹介してくれていて、全部で9通応募してくれました。どのコメントも力作でしたが、「三島由紀夫が読みたくなった。」という出だしの殺し文句で始まり、短い中にもこの異色作を読みたくなる気持ちを引き出すような内容で、選考委員から高く評価されました。
今年度の傾向として、明治・大正などの文豪の作品、現代J文学、海外文学、ミステリー、ノンフィクション、エッセイ、さらには児童書や詩やライトノベルなども含まれ、みなさんの読書の関心の広さを印象づけました。ただ流行を追うのではなく、それぞれの選んだ、心に残った作品が選ばれていることも好感をもって受け止められました。
コロナ対策での生活はまだまだ続きそうです。いろいろと不便をきたしていることもあるかと思いますが、こんな時代だからこそ、そこから生まれた時間を読書などに有効に使って、皆さんの学生時代の思い出に残る読書の経験が得られることを願っています。
立命館生協理事長 文学部教員 加國尚志
大川先生の講評
みなさん、読書マラソンに応募をありがとうございました。今年度はコロナ禍という事もあり、来店することがままならないこともあり、例年よりもコメント数が少なくなってしまいました。特に、OICの応募が少ないのが気がかりです。ネットでの応募も可能となっていますので、OICのみなさんは奮って参加してください。
今回は、どのような点に着目して、審査委員のみなさんがどんなふうにコメントを選考しているのかということを通じて、こういうコメントを書いてほしいなあ、という思いを伝えたいと思います。
選考に関しては、事前に数名の審査委員のみなさんで、独立に選考を進めます。そして、その案を持ち寄って協議して決定するというスタイルです。
この中で特筆するべきことは、コメント大賞クラスのものになりますと、個々独立に選んでいるのに、ほぼ全員がある方のある作品を推すことがままあります。こういう時は、「やっぱりねえ。」、「このコメント読ませますよね。」、「読みたくなりました。」という言葉が思わず漏れます。では、このようなレベルのコメントには、どのような特長があるのでしょうか?
第一の特長は、「面白い」とか「すごく」といった形容詞や副詞を使っていない点です。自分もそうですが、確かに、読んだ当人はすごく面白かった本だからこと紹介したいわけで、そういう思いを持つのは当たり前です。しかし、「すごくおもしろかった。」と書かれても、選考する私たちには「思い」は届かないのです。
そういった形容詞や副詞を使わずに、もっとみなさんの個別具体的な行為や心の変化みたいなものが書かれていると、そういったものを通じて、コメントを読む私たちは「この本は、この人にとって面白かったんだな。こういう読書体験をしてみたいな。ちょっと読んでみようか。」という風に心が動きます。
第二の特長は、 個別具体的な行為や心の変化について、うまいたとえを用いたりして、客観的にわかりやすく相手に伝わるように工夫されている点です。この工夫がないと、コメントを読む側には「 この本は、この人にとって面白かったんだな。 」とまでは、なんとなく伝わるのですが、「 こういう読書体験をしてみたいな。ちょっと読んでみようか。」
というレベルまで気持ちが揺り動かされないのです。
これからコメント大賞に応募してみようと思うみなさんは、是非、以上の2つの点に気をつけて応募してみてください。え?具体的にどうしたらいいかわからないって?それは敢えて書きませんでした。なぜなら、ある本の読み方は十人十色、その感想の持ち方も十人十色であるがゆえに、上記2点を踏まえたコメントの書き方も十人十色だと思うからです。色々と試行錯誤することを大切にしてください。学生時代にはそういう時間的余裕がありますので。
経済学部教員 大川隆夫
受賞者の声 ペンネーム アカイトヲコ
私がこの本に出会ったのは、2020年の夏でした。春から社会が一変してしまって、違和感が日常になりつつあった頃です。慣れていくという過程は辛いもので、後ろ向きになることも多かった季節でした。音楽も、芝居も、ラジオも、執筆も、変わってしまった世界ですら何一つ諦めずに生きていく星野源さんの姿に勇気を貰い、私自身も今の時代に意味を見いだして生きたいと思います。
受賞者の声 ペンネーム りぎたそ
最初何の事やら分からない位驚きました。憧れの方への文章が誰かに伝わったことが嬉しいです。ありがとうございます。
サバイバルの様な世の中ですが漫画でも小説でも文学に支えられながら何とか形を保ちつつ奇妙な世の中を漂っていきたいです。
賞品何が貰えるか楽しみです。
受賞者の声 ペンネーム ナス星人
この度はグランプリに選出いただき、非常に光栄です。価値観や感受性の相違から、1冊の本に対し誰もがぴたりと重なるような同じ感想を抱くことはできません。その中で、読書を経て得たものを言葉に残すことは、自分の内面を鏡に映していく作業のように感じます。そしてそれが共有されることで、1冊の本に自分にない視点という要素が加わります。そういう意味で、こうした活動によって読書が個人の営みを越えるのだと感じました。
グランプリ
『命売ります』三島由紀夫 筑摩書房
ペンネーム ナス星人

一番心に残ったことば (生きたいという欲が、全て物事を複雑怪奇に見せてしまうんです。)
三島由紀を読みたくなった。そんなときに本屋で見つけたのがこの一冊だ。まず何よりタイトルが凄い。『命売ります』のシンプルな文字がその内容のインパクトを一層引き立たせている。読む前からハードルが上がっているようにも感じたが、読了後にはその高められた期待がはるかに超えられる結果となっていた。物語は自殺に失敗した青年が自分の命を売りに出すというショッキングな場面から始まる。命の危機に対して、初めは飄々としていた青年が徐々に死の恐怖に飲まれていくまでの様が、スリルとロマンスに彩られて描かれたエンタメ小説の怪作だ。
準グランプリ
『読書間奏文』藤崎彩織 文芸春秋
ペンネーム りぎたそ

花束。それが私の憧れの人がピアノを弾き始めた理由。友人が発表会で花束を受け取る姿に憧れ、彼女はピアニストへの道を進み始めたらしい。ふと本を閉じ考える。私のピアノを弾く理由。沢山あった。好きな人のために弾きたい日も、何も考えられない程に落ち込んだ私を慰めるために弾いたこともあった。ただ1番の理由は私の音が好きだと言ってくれた人のためだった。目を閉じ鍵盤に指を落とす。私の世界が紡がれる数分間この世界を好きという人に私は生きたいのだ。この本は私にそのことを思い出させる。私は今日も小さな世界に音を落とした。
『よみがえる変態』星野源 文芸春秋
ペンネーム アカイトラ

一番心に残ったことば (生きた証や実感というのは、胸の中にある心の振り幅の大きさに比例するのだ。)
「よみがえる変態」は2012年彼がくま膜下出血で活動を休止した時期のことも書かれている。彼は、途方もない痛みや死の可能性を目の当たりする恐怖の中でも、何ひとつ投げ出さなかった。入院生活の辛いことにも入院生活の中の小さな喜びにも平等に真剣に向き合って、生きていくことで掴めるものを諦めなかった。 きっと彼はこれからも、何ひとつ諦めないだろう。音楽も、芝居も、ラジオも、執必も。欲張りで、素敵じゃないか。私は、彼がこれから生み出していくものが楽しみで仕方がない。
『陸遊詩選』一海知義 岩波書店
ペンネーム 汽包

一番心に残ったことば (向使し愁い無くんば詩を得べけんや)
中国文学史における大詩人陸遊。数多の制約のもとで詩はより自由な、闊達な境地を拓く。教科書で暗唱する詩句のみでは語れない。ユーモラスにして圧倒的に"新しい"世界へ誘う百五十首あまりの精選。
生協理事長賞
『砂の女』安倍公房 新潮社
ペンネーム ナス星人

一番心に残ったことば (下に気をとられたときが、そのまま破滅のときなのだ。)
中三の秋、クラスが受験に向けてピリピリと張り詰めた空気の中、前の席の男子に借りて夢中になったのがこの一冊だ。休暇に虫捕りに行った男が砂穴の底に埋もれゆく一軒家にそこに暮らす女と閉じ込められ、脱出を試みるという設定にまず引き込まれた。しかし最も興味深いのは最終的に彼が脱出に失敗し続けるのでも成功するのでも絶望して諦めるのでもなく、チャンスを前にしても実行する気を失うという所である。その様が蟻地獄に飲まれていく様で印象的だった。突飛な話のはずが描写や語り口が妙に生々しく、私も静かに砂に沈むような心地になった。
ふらっと賞
『らくだい魔女と冥界のゆびわ』成田サトコ ポプラ社
ペンネーム 蒼天

一番心に残ったこと (児童書とは思えないテーマと表現の仕方)
子供の時に読んだ児童書を大学生になり、「大人」として読み返すと新たな発見があった。「友人のために自分が死ぬ」表現に幼い脳みそはついていくことができなかった。そもそも死というものがひどく曖昧だった。しかし読み返してみると児童書の域をはるかに超えた作品だと思った。主人公のフウカは親友のカリンに対して「私の命とひきかえに助けたい」と素直に即座に決断している。自分だったら我が身大切さに親友を見殺しにするかもしれない。信頼関係とは何かを婉曲な表現を使わず書いているからこそ小学生の私に刺さり、大学生になっても読み続けているのかもしれない。
『The Indifference Engine』伊藤計劃 早川書房
ペンネーム オキタルミカ

一番心に残ったことば (ぼくは、ぼく自身の戦争を、どう終わらせたらいいのだろう)
近未来。内戦終結直後のアフリカ。家族を殺され、その復讐のためだけに少年兵に志願した主人公は、戦後、その憎しみと怒りの「根源」を消すために、とある「処置」を受けるが...。平和への努力。そして平和への願いは非常に尊い。しかし、そう考えているのは戦争当事者たちもそうかもしれない。それでも彼らを突き動かすのは、家族を殺された、愛する人を奪われた、そんなパーソナルな感情であるのかもしれない。復讐につぐ復讐。そうして拡大していく悲劇。はっきり言って救いはない。救いはないが、直視しなければいけない。これはSFなどではない。
『古都』川端 康成 新潮社
ペンネーム DENG
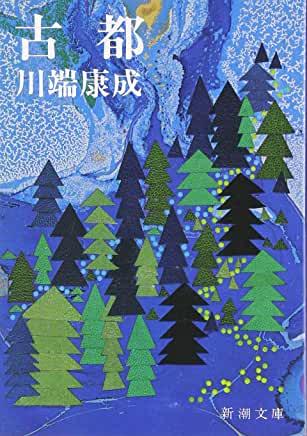
一番心に残った場面 (町は灯がつき、しかも、薄明るさを残していた。千重子は舞台の勾欄に寄って、西をながめた)
『古都』を三回読んだが、気になることは毎回に変化した。まだ京都に行ったことがなかった時、この本を初めて読んで、時代祭や祇園祭の描写が気になり、日本の伝統的民俗を知った。初めて京都に住むようになったとき、この本を読んで、文化の古都で、西陣織や北山杉の職人のように、様々な普通の人々の生活が気になった。京都に住んだ後、この本を読んで、西洋生活の影響による古都の変容が気になり、小説が古都の守りと無力さを示した。今、この歴史の変遷と『古都』を振り返ると、伝統と現代の間で、京都は独自の道を歩んでいる。
リンクショップ賞
『青の数学』王城 夕紀 新潮社
ペンネーム ゆず

一番心に残ったことば (やり続けていれば、いつか着く。)
真っ白な紙に一行の数式。これを解けと言われても、情報、少なすぎないか...?私の頭も真っ白になり、何もできずに解答時間が終わる。私は数学が苦手だ。正直、数学が好きな人の考えが理解できなかった。この本に出合うまでは。
真っ白な紙に数式が一つ。そこからただ一つの答えに向かって突き進んでいく。登場人物達が解答を導き出す時間は宇宙を彷彿させるほど美しく、自由で、神秘的だ。数学の美しさを垣間見て、今は少し、ほんの少しだけ数学のことを好きになれた気がする。
リンクショップ賞
『繁栄 上・下』マット・リドレー 早川書房
ペンネーム AR

「繁栄(上)」
一番心に残った言葉 (テクノロジーは分業によって可能になり、市場での交換がイノベーションをもたらした。)
市場の前提として分業がある。これは一見つまらない特徴だと感じていた。しかし、分業はとんでもない、すばらしい特徴であったことを思い知らされた。分業が我々の生活を豊かにしていたのだ。また、市場経済が生まれるずっと前から分業は存在していた。分業によって農業が生まれ、都市が生まれ豊かな生活を享受できるようになったのだった。加えて、分業によって他人とのかかわりを、ある意味強制的にもつ。これによって信頼することを人間は知った。この本を通じて自分ひとりで行動する無力さ、意味のなさを知らされた気持ちになった。
「繁栄(下)」
一番心に残った言葉 (壮大な目標や中央集権的な計画は、政治と同様、援助の世界でも長い悲惨的な歴史を重ねてきた。)
これまで多くのことは、偉い人や声の大きい人のような一部の人の掛け声の元で行われることが多かったように思われる。そうした物事をトップ・ダウンというらしいが、そうした動きは決して上手に機能しなかった。事実、イノベーションのほとんどは官営企業ではなく新進気鋭の民間企業が生み出している。また、イノベーションが起きる根本として「対話」があると述べている。アイデアが共有されることで、それを改善し、蓄積されていくらしい。ここで分かったことは、人と関わりあうことは天才一人の力よりも強いということであった。
OICショップ賞
『神様のカルテ』夏川 草介 小学館
ペンネーム しおっち

一番心に残ったことば(「本人にどう話すかを考えるんだ」私は医者である。治療だけが医者の仕事ではない。)
医者の仕事は病を治療すること。誰もが信じて疑わない。今なんて特にそうだろう。でも、私はあえて違うと言いたい。
どんなに医療技術が進歩しようと、全員が救えるわけではない。神の手を持つ医師にも不可能はある。そして人の生死は神様の領域だ。人間がどうにかすることはできない。治療法もなく、ただ死を待つ人に出来ることなんて限られている。
だからこそ思う。病を治療するだけが、彼らの仕事ではない。
人と向き合い、死に向き合うのも、彼らの仕事なのだ、と。